今年の夏は酷暑が続き、その上、各地で豪雨による被害が出た。
その情況は、直ちにテレビで放映される。河川の氾濫、家屋や家財の流失、人々の表情・・・・。それらを見ていると、暑いぐらいでグチをこぼしてはいられなくなってくる。
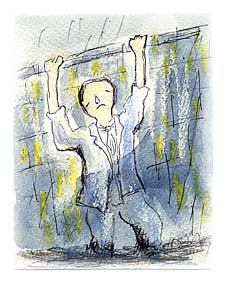 そしてはるか昔、水害に見舞われたときのことを思い起した。
そしてはるか昔、水害に見舞われたときのことを思い起した。
阪神大水害と呼ばれたもので、昭和13年7月5日。私は小学校の2年生であり、東神戸に住んでいた。
長雨のあと、六甲山系全域にわたって山津波がおこり、神戸から西宮までの各河川が決壊し、大被害を生じたのだという。
その日私は在宅していたので、休校の警報が出ていたのかと思っていたのだが、それは間違いらしい。何人かの旧友たちは、登校したものの帰れなくなって困ったと、その日のことを話しているから。
そういえば、父親も、朝、いつものように勤めに出かけていた。とにかく急激な浸水であったのだろう。私はズル休みをしていたのか。
まず思い浮かぶのは、玄関の土間に水が入りこんできたときのこと。母親が、古いじゅうたんのようなものを敷居の上に積み上げたが、すぐ追いつかなくなってしまった。
次の光景は、階段の上から見下していたとき。持てるだけの物を2階に運び上げたそのあとだったと思う。水はじわじわと上ってくるのだ。もしもこの水が止まらなくなったら。そう思うと、泳げない私は、恐ろしくてたまらなかった。
それから忘れられないのがおにぎりの味。あれはどういうふうにして配ってもらったのだろう。水の勢いが止まり、ほっとしてからにちがいない。お腹はペコペコだ。かつおぶしと梅干しぐらいしか入っていなかったと思うけれど、こんな美味しいものはないと思って食べた。
道路は川になっている。朝つとめに出かけた人たちが、下半身水浸しになりながら帰ってくる。2階の窓から父親の帰りを待つ。その姿を見つけたときの嬉しさ。「そちらは危ないからこっちの塀につかまって」と、上から叫んだものだ。
私の家は、六甲山から瀬戸内海に注ぐ住吉川の流域にあり、水が引いてから、その川の方へ見物に出かけた。トラックぐらいの大きな石が、いくつも山から流れついて居座っていた。
谷崎潤一郎は、阪神間のあちこちに移り住んだが、この住吉川畔にも住んでいたことがあるらしい。小説『細雪』にこの水害の場面が出てくるのは、自身の体験があるからだろうか。
テレビはなくても新聞やラジオで報道されるから、親類や知人から、見舞品を送ってもらっていたようだ。
「天皇陛下からお金をもらった」と母から聞いたときには驚いた。天皇は神なのである。写真もまともに見てはいけないという教育を受けていたからびっくりした。神さまはお金持ちなんだなあと。天皇という名で、国が見舞金を支給したのであろうけれど。
町が復旧するまでの数ヶ月間、甲子園球場のすぐ南側の借家に移り住んだ。隣町の鳴尾小学校に通ったが、近辺に小学校がないほど人口が少なかったのだろう。
近年経営不振のため閉園になったが、甲子園には阪神パークという遊園地があ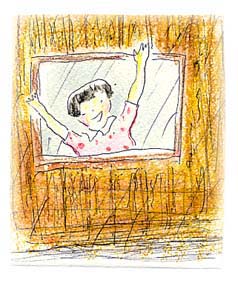 った。当時そこで鯨を見たというと、皆、疑わしそうな顔をする。しかし、紀州の太地でとれたゴンドウ鯨8頭を、特設プールに入れ人気を呼んだ。半年で死んだ、と記録にも残っているのである。
った。当時そこで鯨を見たというと、皆、疑わしそうな顔をする。しかし、紀州の太地でとれたゴンドウ鯨8頭を、特設プールに入れ人気を呼んだ。半年で死んだ、と記録にも残っているのである。
さて決壊した住吉川は、立派に護岸工事が施され、今やその川の上を、人工島六甲アイランドに行き、六甲ライナー電車が走っている。
その電車に乗ると、私のなつかしい町が見渡せる。水害にあい、空襲にあい、そして9年前には大地震にもやられた町。
昭和4年に建築され、当時としては珍しい堂々たる鉄筋3階建ての母校。2年前には、昔の面影を残したまま建て替えられたが、その小学校もみえる。
この小学校には、水害のときも、地震のときも、避難民が仮住居したことだろう。
---ああ 今は昔。
(22)66年前の水害
[2004/8/17]

