新聞の別紙を開いたら、ランボーの詩「地獄の季節」の一節が出ていた。ひときわ目につく太くて大きな活字で。
 この天才詩人は、20歳で早や詩作を断ち、放浪の末アフリカに渡って交易商人となり、武器取引にも手をのばしていたらしい。紅海沿岸の不毛で、きな臭い現状も伝えながら、その特集ページは作られてあった。
この天才詩人は、20歳で早や詩作を断ち、放浪の末アフリカに渡って交易商人となり、武器取引にも手をのばしていたらしい。紅海沿岸の不毛で、きな臭い現状も伝えながら、その特集ページは作られてあった。
おかげで私は、はるか昔、ランボーの詩に親しんでいたころのことを思い出した。小林秀雄の紹介文に触発されランボーを読むというのは、当時の学生たちの流行だったのだろうか。今から思うと気恥かしいのだが、声を出して朗読しあうことさえした。仲間の中には仏文専攻の人もいて、原語で読んでくれたりした。その発音が正しいかどうかわからないが、やっぱり詩は原語でなければと、うなずいて聞いていたものだ。
ランボーの詩をわかって読むのではなく、わからないところにひかれていたのだろうと思う。
過去を振り返ることなく、安穏な生活は唾棄して砂漠をさまよい、最後は肉腫のため右脚を切断され、37歳で死ぬ。その生きざまがすごい。世間の枠組みの中でもがいている若者たちにとって、ランボーの詩は輝いてみえた。
無気力な顔をした大人たちのようにはなりたくない、常識に反逆しよう……とまあそこまではよかったのだが、浅はかな若者心理は、悪いことができてこそ一人前というふうなところに走る。
飲めもしないのに、お酒ぐらいは飲めると飲んでみたり。親や教師に楯突いたり。
何かをすると、威張って仲間うちに報告する習慣があった。
たとえば、無料で郵便を出す方法を思いついた友人がいた。どうするかというと、私が出した葉書の文面の行間に、その人は新しく要件を書き込む。そして表に<宛名人死去につき差出人に返却されたし>という付箋をつけて投函する。そうすると差出人の私のところに戻ってくる。つまり片道の郵便料で往復できたことになるのである。こういうことは思いつくまでが楽しいので、私が半分タダの葉書をもらったのは1回きりであったけれども。
私も悪いことをして1人前になりたくて、キセル乗りに挑戦したことがある。新幹線でキセル乗りが見付かったと新聞記事に出ることがあるが、そんなだいそれたことではなく、ごく近距離のものである。ドキドキしながら出札口を出たとたん、「できたあ!」とよろこんで友だちの肩に抱きついたら駅員さんに呼びとめられた。あまりの幼稚さに怒る気にもなれなかったのか、「もうしてはいけませんよ」と一言いわれただけだった。罰金もとられなかった。
学生アルバイトは盛んで、街頭で広告版を配る仕事のため新聞社に出入りしている中に、奥の廊下から隣接の映画館の内部に出られる道を発見した。スリルと共にその道をたどっては、何度も映画を楽しませてもらった。しかし映画館の人は気がついていたのではなかったろうか。貧乏学生のことだから大目に見てやろうと、ゆるしてくれていたのかもしれない。
いっしょうけんめい歯向かうのだけれど、世間の枠はなかなか手強い。その中で、少しずつ、自分らしい大人になるための道を手探りしていたあのころ。敗戦から月日が経っていなくて、大人も若者も貧乏であるという連帯感があった。何かしら暖かな目で、若者のはねかえりぶりを包んでもらっていたような気がする。それは幸せなことであったと、今振り返って思う。
そのありがたいロハの映画館ではフランス映画をよく見た。学生たちに人気があったのである。帰り道、男の子たちがしゃべっていた。「女はやっぱり陰影のある顔がいいなあ」と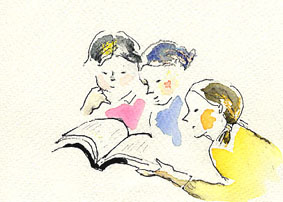 。
。
帰るなり、顔を鏡に映してみたら、まんまるくはちきれているだけで、影などどこにもない。どうしたら影ができるのだろう。悩まなければと思いつき、はて何を悩んだらいいのだろうと悩んだ記憶がある。
今や影ばかりのわが顔になっているのだが、そのころのことを思い出すと、おかしくなってくる。
ダイエットに憂き身をやつしている若い娘さんたちに、「そのピチピチがいいのよ。命短しなのよ」といってあげたい。
(18)ランボーを読んでいたころ
[2004/3/2]

