56回目を迎えたNY映画祭は、今年(2018)も9月末から開催された。メイン部門ではカンヌ、ベルリン、ヴェネツィア映画祭での受賞作をはじめ、世界で話題の新作が揃うので、近年、海外の映画祭に出かけなくなった私にとっては一挙に最近の話題作を観ることができる絶好の機会である。メイン部門以外でも回顧展やドキュメンタリー、実験映画、新しいテクノロジーの部門など幅広く数多くの作品が紹介され、とても網羅的に観ることはできないが、私は毎年回顧展やドキュメンタリー部門を楽しみにしている。
プレスと配給などの映画業界者向けには映画祭が始まる2週間前から1日2、3本の作品が上映され、これには記者会見がつくこともある。今回試写がなかったので一般上映の切符を買って見た作品について書きたい。
日本映画の研究家が映画製作?
今年の映画祭のプログラムを見て私が即座に興味を持ったのは、J.L.アンダーソン監督の1967年の作品『Spring Night, Summer Night (春の宵、夏の宵)』(詳細はSpring Night, Summer Night)である。この監督とは、1959年に英語による先駆的日本映画の本Japanese Film: Art and Industry (Charles E. 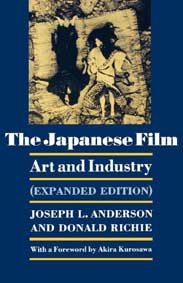 Tuttleより出版、その後82年に Princeton University Press より拡張版が出ている)をドナルド・リチーと一緒に書いたジョゼフ・L・アンダーゾンではないかと思い、インターネットで調べてみると、やはりそうであった。
Tuttleより出版、その後82年に Princeton University Press より拡張版が出ている)をドナルド・リチーと一緒に書いたジョゼフ・L・アンダーゾンではないかと思い、インターネットで調べてみると、やはりそうであった。
私がアンダーソン氏の名前を知ったのは、1979年にNY大学に留学してからであるが、実際に会う機会は私が86年にNYのジャパン・ソサエティーの映画部門で働くようになってから訪れた。当時ボストンの教育テレビで働いていた彼が日本の無声映画の研究をしていると聞いて、89年にジャパン・ソサエティーとアメリカ映像博物館が共催で上映した日本の無声映画特集に参加していただいた時である。アンダーソンさんには英語による活弁の実演を少し披露していただき、パネル討論にも参加していただいた。
その時に研究中と伺っていた、川上音二郎と貞奴の海外巡業についての本は、Enter a Samurai: Kawakami Otojiro and Japanese Theater in the West, Volume 1 and 2 (Wheatmark, 2011) として出版されている。
その次にアンダーソンさんの姿を見たのは、2年前の2016年の秋、明治学院大学で開催された海外での日本映画研究についてのシンポジウムで上映されたビデオの中であった。日本映画紹介の分野でアンダーソンさんの評価が不当に低いことを日頃から残念に思っている明治学院大学のロランド・ドメニグ先生が、健康上の理由で東京までの旅が出来なかったアンダーソンさんにインタビューするためにボストンへ赴いて撮ってきたものであった。アンダーソンさんは演劇や映画の美術の仕事に関わっていた事、父の仕事の関係で第二次世界大戦後の連合軍占領中の日本へ行った経緯、日本女性と結婚し、日本映画や演劇の研究をしていたこと、そして日本公開のアメリカ映画の字幕製作に関わったことなどを話されていた。
『春の宵、夏の宵』
今回の上映にアンダーソンさんは、やはり健康上の理由で会場には来ることが出きなかったが、彼のオハイオ大学映画学部の学生で一緒に映画製作をしたフランク リン・ミラー、記録を担当したジュデイ・ミラー、本作の修復を担当したピーター・コンハイムが、上映後、討論に参加した。
リン・ミラー、記録を担当したジュデイ・ミラー、本作の修復を担当したピーター・コンハイムが、上映後、討論に参加した。
映画はモノクロで、プログラムによればアパラチアの炭鉱の町ということだが、畑や森が続き、人の姿があまりない寂しげなコミュニティーの雰囲気がリアルに浮かび上がる。慎ましい白人の家で、7歳ぐらいから20歳ぐらいまでの男女数人の子供たちと夫婦が食卓からはみ出すように座って、ガヤガヤと夕食の風景が展開し、隣の部屋ではおばあさんが一人、テレビを見ながら食事をしている。一番年上の息子と父親は口論になり、この親子関係はうまくいっていないようだ。息子が、妹であるらしい若い女性の洗面所での着替えを盗み見する場面があり、映画が始まって程なく、何かを予感させるような、心を逆なでするトーンとなる。
このような田舎では娯楽もほとんどなさそうで、年長の息子と娘、母親が着飾って近くの居酒屋に車で出かける。そこではいかにも地元の人間らしい人たちが、ビールを飲み、西部劇でよく聴くバンジョーがリズムの速い賑やかな音楽を奏で、ダンスをしている。そこで、母親はビールを飲んで男たちと大いにはしゃぎ、息子の方は妹にちょっかいを出した男を突き飛ばす。兄妹は車で何もない暗い道を戻る。そこで兄は車を止めて、妹に襲いかかり、抵抗していた妹もそのうち草むらで彼を受け入れるようになる。
ほどなく妊娠した娘を巡って家族や町に波紋が広がるが、彼女はそれほど気にしていない様子でどんどんお腹が大きくなっていく。
黒の目立つモノクロの画面は、森や野原でも偏狭なコミュニティーの閉塞感を感じさせる。大きな車体のキャデラックが溢れ、瓶入りコーラが自動販売機で売られていて、飲み終わった瓶を置く棚が販売機の近くに設置されている。いかにも60年代アメリカの日常の風俗的イメージが興味深い。
製作史
上映後の討論でフランクリン・ミラーは、オハイオ大学大学院映画学科の学生たちとこの映画を2年がかりで製作し、脚本はフランクリンとアンダーソン、それに学生のダグ・ラップと三人で書き、撮影はデヴィッド・プリンス、ブライアン・ブラウザー、アーサー・スティフェルという三人の学生が共同でおこなったと語った。オハイオ州南部の田舎にロケハンに行き、地元の人たちをエキストラとして使って撮影、主役の兄役のテッド・ヘイマーディンガーと妹役のラルー・ホールは演劇を勉強している20代前半の学生だった。父親役の俳優ジョン・クロフォードは実は29歳だったというのは、予算の少ないインデペンデント映画らしいエピソードだが、その役者がそこまで若くは見えなかったので、意外な事実に観客はへえーっと苦笑いした。その他の俳優も、地元の演劇界からスカウトしたとのことだった。
関係者一同で、参考にエルマンノ・オルミの『婚約者たち』(63)を見たそうだが、なるほどモノクロで静謐な画面が驚くほどシンプルでありながら、独特の情緒が醸し出されるオルミの映画との共通点はあるかもしれない。出演者はロケ地で事前に時間を過ごして、その地方の方言を学んだ。記録担当のジュデイ・ミラーは、撮影現場は虫がたくさんいて大変だったが、とても和気あいあいとして楽しかったと述べた。
フランクリンによれば、完成した映画は1967年にイタリアのペサロ映画祭で上映され、当時のNY近代美術館 (MoMA) 映画部門部長のウイラード・ヴァン・ダイクが見て気に入ってくれたので、広く観られることを期待した。しかし現実は厳しく、68年にNY映画祭に一旦招待されたものの、ジョン・カサヴェテス監督の『フェイシズ』(68)を入れなければいけないからと、その後落とされてしまったそうだ。
やっと商業的配給業者に買ってもらえたが、その会社はキワモノとして売り出すことを考えて、『ミス・ジェシカは妊娠中』という題をつけて、アンダーソンに裸の場面を付け足すように頼んだ。アンダーソンは裸の場面を撮り足し、兄妹のセックス・シーンを再編集して、映画の後ろの方にあった妹が微笑むショットをこの場面の最後に入れたと言う。しかし新しい題名が裏目に出て、「妊娠」という言葉があるため南部では本作は上映不可能となり、いつの間にか本作は忘れられてしまった。
フランクリンは、再編集前のプリントを一本持っていたので、その後アイオワ大学で教職を得た時に授業で繰り返し見せていた。その後、アイオワを離れ、年月も経ってこの映画のことも忘れ去っていた。
修復まで
ある日、アイオワ大学での教え子、マイク・シュミットからフランクリンに電話があった。アイオワの洪水で被害を受けた大学の建物内のものの救出作業中、フ ランクリンの名前が書かれた段ボール箱があるが、これはどうしましょうか、という質問であった。そこでフランクリンの記憶が蘇り、それは自分が協力して作った1960年代の映画なので送って欲しいと頼み、久しぶりに見たのが本作である、という話に観客はため息をついた。
ランクリンの名前が書かれた段ボール箱があるが、これはどうしましょうか、という質問であった。そこでフランクリンの記憶が蘇り、それは自分が協力して作った1960年代の映画なので送って欲しいと頼み、久しぶりに見たのが本作である、という話に観客はため息をついた。
シュミットも本作を見てその価値を直ちに理解した。シュミットはNYのインデペンデント系配給会社、キノ・インターナショナルで働いていて、本作を2005年に巡回プログラムに入れた。そこで本作を見たニュー・メキシコ州アルバカーキーで名画座ギルド・シアターを運営しているピーター・コンハイムが、本作は修復されるべきだと思い、映画の修復保存プロジェクト、シネマ・プリザヴェーション・アライアンスのパートナーのロス・リップマンにDVDを送った。その後調査をしたら、再編集版のオリジナル・ネガも見つかり、それとともにフランクリンの持っている使い古されたプリントが、ロス・リップマンが働く映画修復保存で有名なカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)映画・テレビ学部に寄贈された。
しかしこの修復には資金が必要で、しばらくこの二本のプリントは眠ったままであったが、本作を見たニコラス・ウインディング・レフン監督(カンヌ映画祭で脚本賞を受賞した『ドライブ』(11)で有名)が資金提供を申し出た。そこで、オリジナル版に沿ってデジタル修復が可能になったという経緯を語った。
観客からの質問となった時、観客の中にエド・ラックマンがいたので私はびっくりした。ヴィム・ヴェンダーズ監督の『東京画』(85)、ソフィア・コッポラ監督処女作『バージン・スーイサイド』(99)、スティーヴン・ソダーバーグ監督の『エリン・ブロコヴィチ』(00)、トッド・ヘインズ監督の『キャロル』(15)や『ワンダーストラック』(17)などで余りに著名な撮影監督で、NY映画祭の常連である。ラックマンはオハイオ大学でアンダーソン氏の学生で、次の作品『アメリカ、ファースト(America First)』 (72) を一緒に製作したと言う。フランクリンはその映画が製作されたのは覚えているが、今現存しているプリントがあるかどうかはわからないとのことであった。
製作費の質問が出ると、当時29,000ドルで作ったというフランクリンの答えで、その額の少なさに会場が驚きのため息で沸いた。近親相姦というテーマが断罪されている訳でもなく自然に描かれていてユニークだという観客の意見に、フランクリンは、偏狭な土地に我々よそ者が行ったので、地元の人たちの態度は険しかったが、一番心配だったのは近親相姦というタブーを撮影していたことだった、とのこと。しかしそれが人々に漏れた時、「そんなことはこのあたりではよくあることだよ」と言われた、というところで観客は爆笑。また、フランクリンはこの映画を通じて、男性の視点の覗き見的な構図が取られていることを指摘した。
この日会場に来られなかったコンハイムの映画修復保存のパートナーのロス・リップマンは、本作の解説をイギリスのサイトに載せている。それによると、コンハイムから是非とも修復保存されるべきだとして、本作のDVDが送られて来たが、他にもそのような要請とともにDVDを連日受け取るリップマンは、忙しさにかまけて見ないまま放っておいた。そして2年が経ち、2008年の休暇中の眠れないある晩、ふとそのDVDが目にとまり、見ることにした。そして数分後に、これは保存すべき作品だと確信した。「これこそ、アメリカ版ネオリアリズモだ。」地元のアマチュアたちが、プロの俳優や駆け出しの俳優たちに混じって出演している。自然光の中のロケーションで、ほとんど物語的な筋はないのだが、それでいてアメリカの知られざる、より現実的な奥深さを描き、ハリウッド映画でもそうでなくても、他では絶対に見ることができないイメージである、と興奮気味に書いている。そして、本作の配給権を買ったキワモノ好きの業者は、当時駆け出しの映画人マーテイン・スコセッシを雇って、編集し直すように頼んだが、「これは完璧な映画で再編集の必要がない」とスコセッシが言ったという伝説のような話を紹介している。(http://old.bfi.org.uk/sightandsound/feature/49794)
40年前のアパラチアの奥深い地方のイメージが鮮やかなモノクロで蘇ったこの映画を観て、この40年間の本作の奇異な運命に私は思いを寄せた。披露されたいくつものエピソードがどれか一つ欠けても、いま現在、我々はこの映像を見ることができなかったわけだ。例えば、洪水の際に、フランクリンの名前入りのダンボール箱が救出されていなかったら……面倒だと思って連絡を滞る人がその間にいれば、そこでこの映画の運命は決まってしまっていたわけである。リップマンがコンハイムから送られた本作のDVDを積み上げたままで、見ることがなければ……資金難で滞っていた修復作業にレフン監督が助けの手を差し延べなかったら……
若き頃、敗戦後の日本に住んだアメリカ人のアンダーソン氏が、その後オハイオ大学で世界的な撮影監督を育て、アメリカ・インデペンデント映画史に残る名作を作っていることに、全てが運命の糸に操られてような不思議さを感じざるをえなかった。
尚、この作品は、2018年11月からインターネット上で無料で公開されるそうだ。

